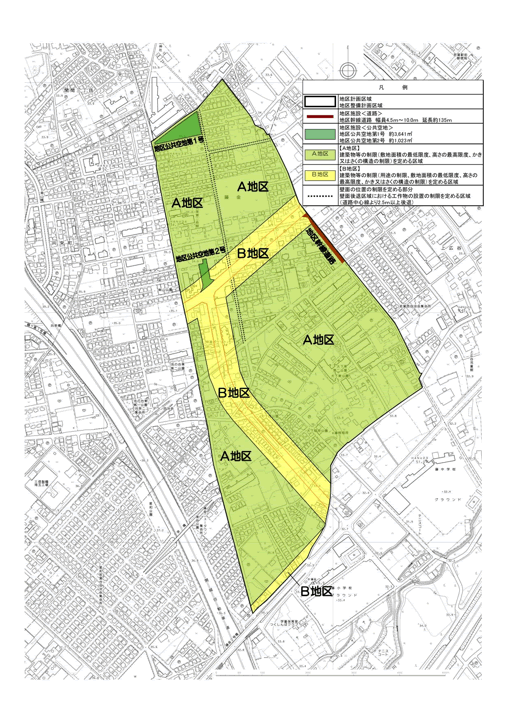共栄第2期地区地区計画 計画書
平成22年3月5日・鶴ヶ島市告示第33号
| 名称 | 共栄第2期地区地区計画 |
|---|---|
| 位置 | 鶴ヶ島市大字藤金字仲道、字大下の全部及び字下前の一部 |
| 面積 | 約32.7ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は、東武東上線若葉駅西口に近接し、若葉駅へのアクセス道路となる都市計画道路3.4.7共栄一本松線、3.4.8共栄鶴ヶ丘線が計画されている鶴ヶ島市にとって比較的重要な地区である。
平坦地で鉄道駅への利便性も良いことから、戸建住宅や集合住宅を中心に宅地化が進行した地区である。
都市基盤施設の整備・改善等や建築行為に対する適切な規制・誘導を行うことにより、都市計画道路沿道については、後背の住環境との調和を図りつつ幹線道路沿道にふさわしい土地利用を促進し、その他については、無秩序な市街化を防止し良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針
地区計画を定める区域は、以下の区分により、それぞれの方針に従って土地利用の規制・誘導を図る。
- A地区
戸建て住宅・中高層共同住宅などを主体とする専用度の高い住宅地の形成を図る。 - B地区
後背の住宅地との調和を図りつつ、生活利便施設など幹線道路沿道にふさわしい複合的な土地利用を図る。
地区施設の整備の方針
既存の道路網を活かし、建築物の新築や建替えなどに合わせた拡幅などの修復的な整備及び地区施設道路の新規整備を行い、歩行者等の日常生活における安全性・利便性や防災性の向上を目指した道路機能の改善とネットワークの強化を図る。
特にオープンスペースが不足している地区の北部においては、新たに公共空地を設ける。
建築物等の整備の方針
良好な住宅地の形成及び幹線道路沿道における周辺住宅地と調和した商業業務地の形成を図るため、本地区にふさわしくない用途の建築物の混在を防止するための建築物等の用途の制限、敷地の細分化を防止し良好な生活環境の形成を図るための敷地面積の最低限度の制限、安全でゆとりある歩行者空間の確保を図るための壁面の位置の制限と壁面後退区域における工作物の設置の制限、秩序ある街並みの形成を図るための建築物の高さの最高限度の制限、災害時に倒壊の危険性のある塀等を制限し敷地内緑化を奨励し潤いのある街並みをつくるためのかき又はさくの構造の制限を行う。
地区整備計画
| 地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 道路 | 地区幹線道路 幅員4.5~10.0m 延長約135m (市道167号線 拡幅) | ||
| 公共空地 | 地区公共空地第1号 約0.3ha 地区公共空地第2号 約0.1ha | ||||
| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | A地区 (第一種中高層住居専用地域) | B地区(第一種住居地域) | |
| 区分の面積 | 約26.4ha | 約6.3ha | |||
| 建築物等の用途の制限 | − | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 | |||
| (1) 工場(ただし、当該規定が定められた際、現に存する工場で、建築基準法施行令第137条の7で定める範囲で増築及び改築する場合を除く。) (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎 |
|||||
| 建築物の敷地面積の最低限度 | 135m2 | ||||
| ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 (1)公共公益上必要な建築物の敷地として使用する場合 (2)当該規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないものを継続して使用する場合 (3)当該規定が定められた際、現に存する所有権その他の権利に基づいてその土地の全部を一の敷地として使用する場合 (4)当該規定が定められた以降に道路後退による残地を一の敷地として使用する場合 (5)当該規定が定められた際、現に同一人が所有権を有している土地について、当該土地の面積を135m2以上ごとに分割し、その結果生じた100m2以上の残地を一の敷地として使用する場合 |
|||||
| 壁面の位置の制限 | 計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路の中心線までの距離は2.5m以上とする。また、軒、出窓、ベランダ及びその他これらに類する建築物の部分についても同様とする。 | ||||
| 壁面後退区域における工作物の設置の制限 | 壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域においては、かき、さく、塀、門、広告物、看板、自動販売機、植栽など交通の妨げとなる工作物を設置してはならない。 (ただし、公共公益上必要なものはこの限りでない。) | ||||
| 建築物等の高さの最高限度 | 25m又は当該規定が定められた際、当該敷地において現に存する当該建築物の高さ | ||||
| かき又はさくの構造の制限 | 道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。(ただし、門は除く。) (1)生垣 (2)高さ0.6m以下の基礎部分の上に透視可能なフェンスを施したもの(宅地地盤面からの高さが1.5mを超えないものに限る。) |
||||
| 備考 | |||||
共栄第2期地区地区計画 地区区分図